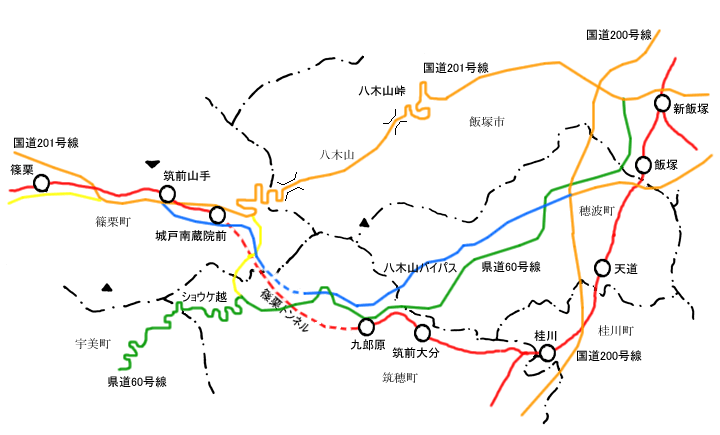| 沿 革
八木山峠とは、福岡と飯塚を結ぶ旧篠栗街道にあり、台地上の八木山集落を抜ける峠である。
旧街道・篠栗街道は、篠栗線のルートとは一致しない。篠栗線は城戸南蔵院前を出ると篠栗トンネルで南東へ進路をとるが、街道はそのまま西進し八木山峠を越え飯塚へと向かう。現在の並行道路である国道201号線は八木山峠を通るが、同道バイパスである八木山バイパスは、篠栗線とほぼ同じルートをたどる。地形的に見ても篠栗線ルートのほうが建設は容易である。
篠栗線のうち、吉塚−篠栗間は1904/6/19に開業した。当時の九州鉄道は飯塚までの免許を取得していたが失効。その後、旧改正鉄道敷設法に残りの部分が指定。しかしなかなか着工されず、鉄建公団の手によって着工、1968/5/25に、篠栗−桂川間に開業を見た。さらに2001/10/6には筑豊本線:折尾−桂川間、鹿児島本線:黒崎−折尾間(短絡線)とともに電化された。
峠に対する勾配区間は、篠栗−筑前大分である。しかし同区間は1968年と近年になっての開業である事から、ルート選択や建設手法などは新幹線的で、勾配は他の峠路線ほど急ではなく(16.7パーミル)、トンネルも長大(4,550m)である。その点を考慮すれば、無関係型に近い標準型といえるかもしれない。
この路線の目的は、筑豊地区で採掘される石炭輸送の為であった。
当初、船越鉄道という会社が設立され、筑豊の石炭を船越湾(筑前前原の西側の湾)まで運び船積みする目的であった。ところが当時筑豊地区で石炭輸送していた九州鉄道が船越鉄道を買収し、1904/6/19に吉塚−篠栗間開業となった。その後延長されることがなかったが、1968/5/25に篠栗−桂川間が開通し全通となった。そのころにはもう石炭輸送は無く、逆に通勤通学輸送が増加し、区分も幹線である。
篠栗トンネルは、延長4550mで開通当時九州一の長さを誇った。建設当初から交流電化断面で建設されていたため、この度の電化工事に際しても大きな支障とはならなかった。トンネル自体はゆるくカーブしており、トンネルに入ってしまうと、入口も出口も見えなくなる。その中を817系電車が100km/h近いスピードで駆け抜けている。
|
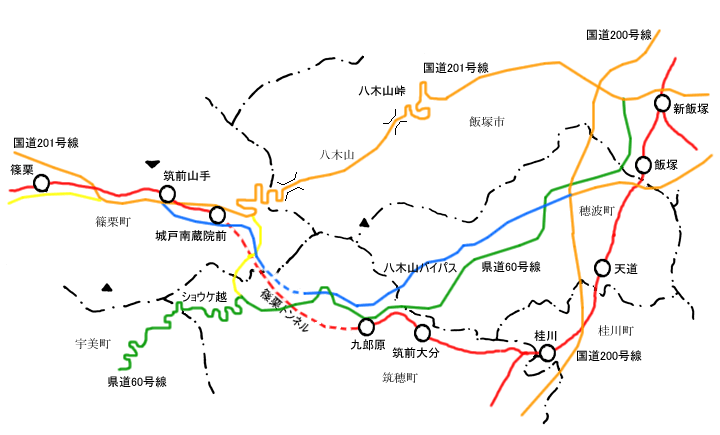
![]()