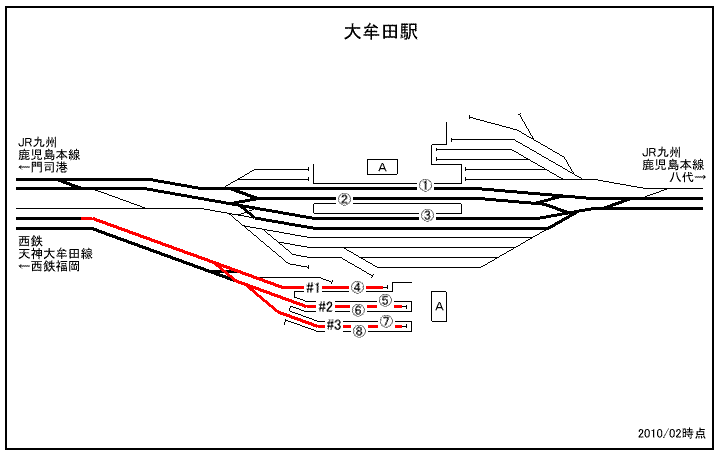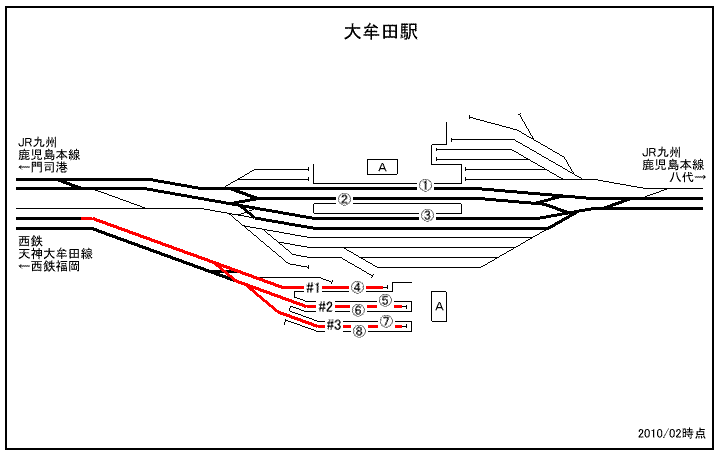大牟田駅は1891/04/01に九州鉄道によって開設された。当時の大牟田周辺における行政・市街の中心地は、銀水駅から東南東約2kmに位置する三池というところであった。しかし三池を経由するには線形上、上下両方向に曲線勾配が発生するために、平坦線である大牟田地区経由の現ルートをとることになったものと思われる。
開業当初は現在地より北側約450mに設置された。線路が通り駅が設置されたことで、三井三池炭鉱の拡充や関連工場等の進出がみられ、三池地区と大牟田地区の繁栄が逆転、官公庁も大牟田地区に移転となった。周辺の発展とともに駅での旅客貨物取扱量も増加したため、駅拡充のために1911年2月に現在地に移転した。
九州鉄道(現・西日本鉄道)が大牟田まで路線を延ばしたのは、1938/10/01に九鉄中島(現・西鉄中島)−九鉄栄町(現・新栄町)を開業したときである。現在の大牟田駅まで延伸されたのは1939/07/01であり、この開業のズレは用地買収の関係であった。大牟田駅は国鉄駅であり、九鉄は国鉄駅に乗り入れる形で大牟田延伸を果たした。現在においても駅全体はJR九州の駅である。この大牟田延伸を経て1939/11/01にダイヤ改正を行い、福岡−大牟田間の急行運転(78分・3往復)が開始された。
以後、九州鉄道は戦時中の陸上交通事業調整法により西日本鉄道となり、現在に至る。
大牟田駅では過去に西鉄の車両の搬入が行われていた。 車両メーカーで製作された車両が狭軌仮台車を履いて国鉄線を大牟田駅まで甲種輸送されてきて、西鉄4番のりば脇の狭軌・標準軌4線区間で標準軌台車に履き替え、西鉄側へ引き渡されていた。現在は新門司港まで海上輸送、新門司港〜筑紫車庫まで陸送となり、大牟田駅での搬入は行われなくなった。そのため引き渡し施設も撤去され、それと思われる遺構が見られる程度の状況となっている。
|