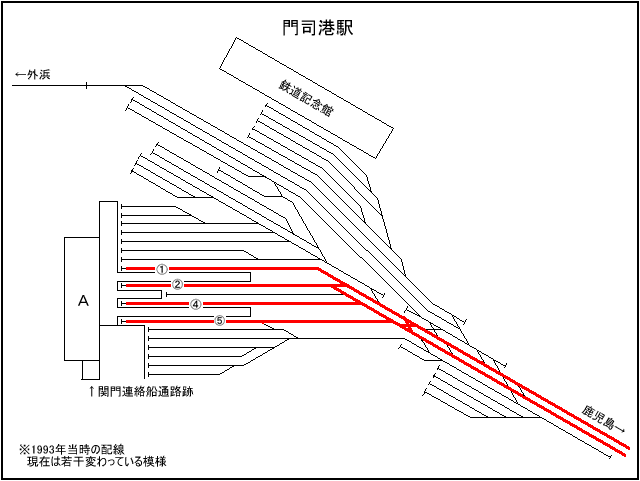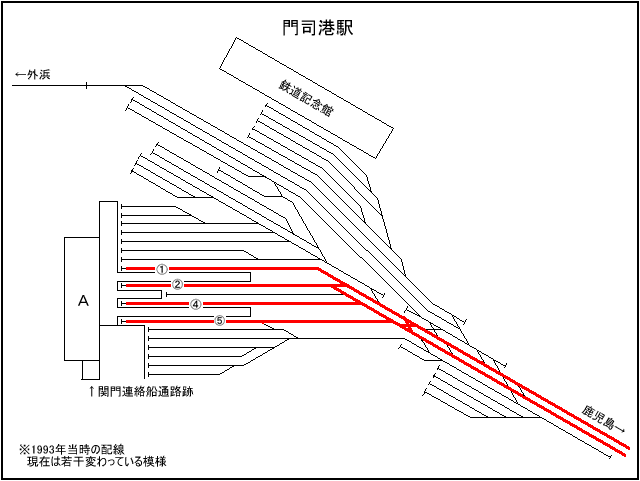| 1891/04/01 |
九州鉄道(初代)が門司(現・門司港)−黒崎間を開業。終端駅として開設。
当初は鉄道記念館アプローチ付近に設置。現位置より東に200m。 |
| 1891/04/23 |
それまで博多にあった九州鉄道本社を門司に移転。(現在の鉄道記念館建物) |
| 1897/04/20 |
門司(現・門司港) −小倉間複線化。 |
| 1898/09/01 |
山陽汽船が下関港−門司港間に定期航路を開設。鉄道連絡船としての役割を担う。 |
| 1901/05/27 |
山陽鉄道下関駅開業に伴い着岸地を下関駅に変更。 |
| 1906/12/01 |
山陽汽船を国有化。 |
| 1907/07/01 |
九州鉄道(初代)を国有化。 |
| 1911/11/01 |
関門連絡船で鉄道車両航送実施。貨物便は下関−小森江間の「関森航路」となる。 |
| 1914/01/15 |
現在の駅舎完成。移転。 |
| 1942/04/01 |
関門トンネル開通を前に門司港駅に改称。 |
| 1942/07/01 |
関門トンネル開通。 |
| 1930/04/01 |
葛葉−門司港−外浜間(貨物営業)開業。 |
| 1961/06/01 |
門司港−久留米間電化。 |
| 1964/11/01 |
国鉄関門航路を廃止。 |
| 1987/04/01 |
国鉄分割民営化によりJR九州が継承。 |
| 1988/11/18 |
駅舎が国宝・重要文化財(建造物)として指定される。 |
| 2004/03/25 |
貨物列車の運行が終了。 |
| 2005/10/01 |
門司港−外浜間休止。 |