JR九州・折尾駅
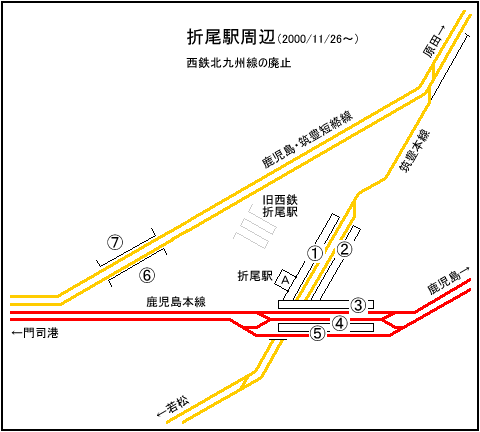
<概要>
型式:単純型
上:JR九州・鹿児島本線・複線
下:JR九州・筑豊本線・複線
構造:デッキガーダー
折尾駅は日本初の立体交差駅である。
1891/02/28に九州鉄道が遠賀川−黒崎間を開業させ、途中駅として折尾駅が設置された。
開業時の九州鉄道折尾駅は現駅部分から300m程度東方にあったと思われている。
次いで同年08/30に筑豊興業鉄道が若松−直方間を開業。こちらも現位置ではなく北方にあった。
これでは両線の連絡はとても不便なため、 4年後の1895/11/13に両線とも立体交差部分に駅を移設し
日本初の立体交差駅として開業する。
現在、筑豊本線の電化区間は折尾−桂川間である。若松までは電化されていない。
これは旅客流動もさることながら、交流電化に際して立体交差部分の上空空間が不足しているためでもあった。
蒸気機関車時代のままの建築限界なのである。
よって2番のりばに張られている電車線はガーダー直前で途切れ、テンションワイヤーだけがガーダーをくぐっている。
折尾駅南方を走る短絡線には折尾駅6・7番のりばがある。そこからすぐ直方よりに、西鉄北九州線との立体交差も存在した。
西鉄北九州線は1914/11/26に折尾駅まで伸びた。その際に短絡線との立体交差も出現した。
2000/11/27に廃止となりガーダー橋はそのまま残された。
しかし1年後には筑豊線電化のため、限界に抵触するガーダー橋は撤去された。
今、折尾駅周辺は再開発事業(折尾地区総合整備事業)が進められ、駅自体も大変身を遂げる予定である。
筑豊本線を鹿児島本線脇に横付けし相互の乗換えを便利にするとともに、駅周辺の区画整理を行うものである。
将来これにより現在の形の立体交差は解消される。
<地図>
・国土地理院『うぉっ地図』:折尾
・マピオン:北九州市八幡西区堀川町
・いくとこガイド:福岡県北九州市八幡西区堀川町 付近
・Googlemap:折尾駅
・国土交通省ウェブマッピングシステム→カラー空中写真
・1974年版
・画像中央。若松方面への短絡線跡地がみえる。黒崎−中間間の短絡線上に6・7番のりばはまだない。
・1・3・5番のりばに列車がとまっている。西鉄北九州線も健在、走行中の電車も見える。
・駅前の広場は現状とは違う。
・1981年版
・画像右端。1974年とほとんど変わっていない。
<沿革>
1891/02/28、九州鉄道(第1次)が黒崎−遠賀川間をを開業させ折尾駅設置。このときの折尾駅は300m程度東方。
1891/08/30、筑豊興業鉄道が若松−直方間を開業させ折尾駅を設置。立体交差となる。
1893/06/30、黒崎−中間間の短絡線開通。
1894/08/15、筑豊興業鉄道を筑豊鉄道に改称。
1894/12/21、筑豊鉄道・折尾−中間間複線化。
1895/11/13、両鉄道が折尾駅を立体交差部分に移設。2社共同駅舎完成。日本初の立体交差駅となる。
1896/04/29、筑豊鉄道・若松−折尾間複線化。
1897/10/01、九州鉄道が筑豊鉄道を合併吸収する。
1907/07/01、九州鉄道が国有化される。
1913/12/08、折尾−遠賀川間複線化。
1916/11/05、現駅舎の完成。
1922/04/01、折尾−中間間複々線化。黒崎−中間間短絡線のうち折尾−中間間の複線化のことか。
1930/05/15、本城信号場(現廃止。今の本城駅付近)−折尾間3線化。線増分は鹿児島・筑豊短絡線。
1944/10/06、黒崎−折尾間複々線化。黒崎−中間間短絡線のうち黒崎−折尾間の複線化のことか。
1961/06/01、門司港−久留米間電化。
1969/10/01、本城信号場廃止。本城信号場−折尾間の短絡線廃止も同時か。
1987/04/01、国鉄分割民営化。JR九州に。
1988/03/13、6・7番のりば(鷹見口)設置。
2001/10/06、筑豊本線:折尾−桂川間、黒崎−中間短絡線電化。
時期不明・・・・・・折尾−中間間の線減。複々線から複線へ。少なくとも筑豊本線電化前だったと記憶している。
<関連リンク>
・折尾駅-今昔物語 ここは折尾の歴史に関してとても詳らかに紹介してある秀逸サイト。折尾に対する愛着が強く感じられる。
・点描 折尾駅 (汽車旅悦楽館→5号館 ふるさとの情景→点描 折尾駅) 筑豊線電化前の折尾駅だが、詩情豊かな画像がすばらしい。
(文責・著作権:脚長ヲヂサン)